
防災にも「心の備え」を!在宅避難・避難所で役立つメンタルケア方法
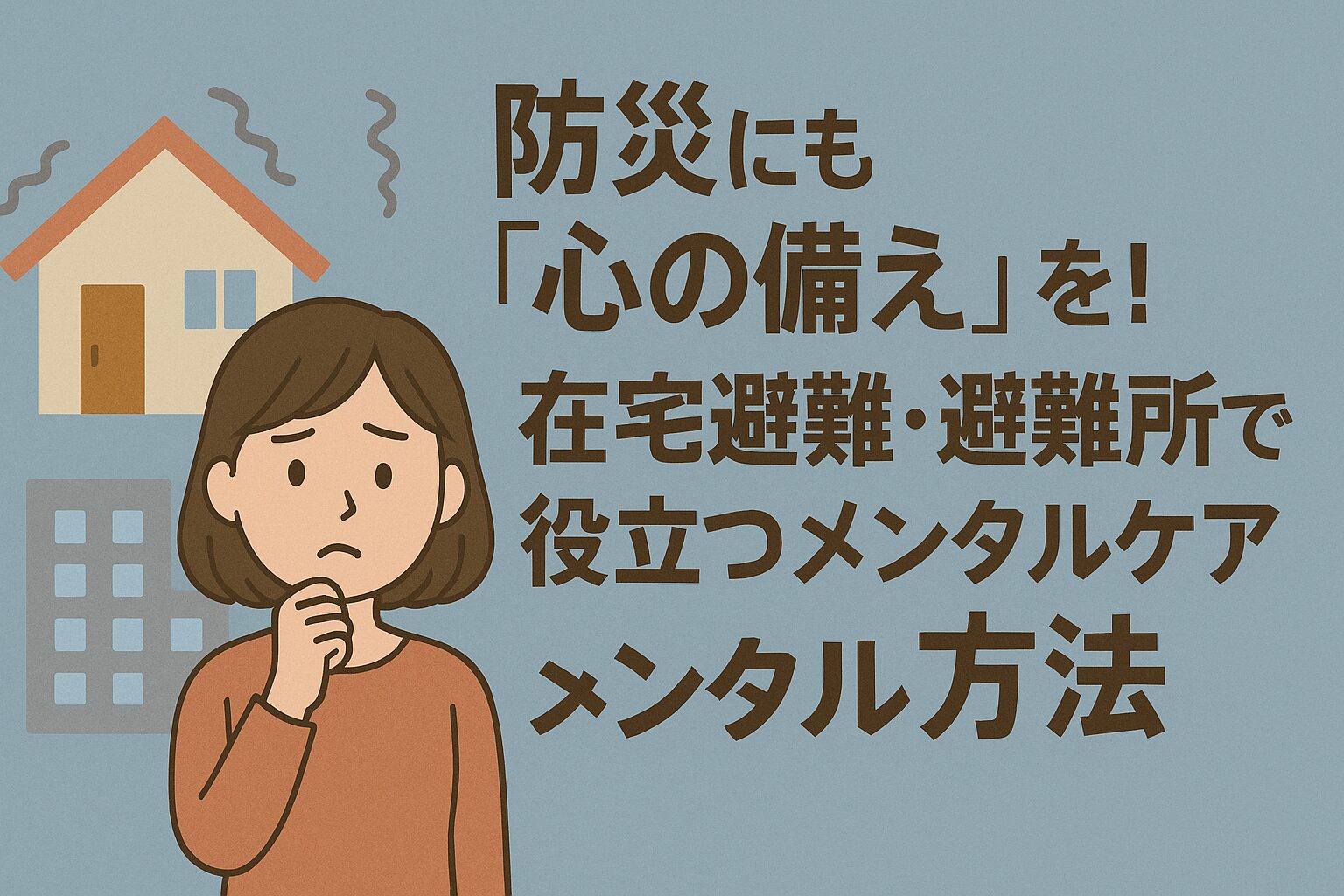
災害が心にもたらす影響とメンタルケアの重要性
大きな災害は私たちの心に深刻なストレスを与えます。
普段は健康な人でも、不安や恐怖、不眠といった精神面の不調が生じる可能性があります。
地震や台風などの直後には強い恐怖心やショックに襲われ、その後も喪失感や罪悪感、生活環境の激変によるストレス反応など さまざまな心理反応 が起こりえます。
こうした反応の多くは決して異常ではなく、非常時における正常な心の反応 です。
時間の経過とともに地域の復興や生活再建が進めば、ほとんどの人は自然に回復していくことが知られています。
しかし、一方で支援不足や被害の大きさによってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)やうつ病などに発展する場合もあり、専門的ケアが必要になる人もいます。
実際、ある研究では大規模災害の1年後にPTSDを患う人は約10%に上ると見積もられています。
だからこそ、「心のケア」は防災においても重要な課題なのです。
メンタルケアの基本は命と生活を守ることから始まります。
災害直後にはまず生命の安全を確保し、安心できる環境と十分な睡眠・休息を得ることが何より大切です。
専門家の加藤寛氏(兵庫県こころのケアセンター)も「被災者の心理的回復のためにまず必要なのは、安全で安心な場所を確保し健康的な生活環境を取り戻すこと」と指摘しています。
安全・安心・安眠という「心の三本柱」を確保するだけでも、人の心はかなり落ち着きを取り戻します。
その上で、被災者自身が少しずつ生活の自立を取り戻せるよう支援することが心のケアの土台となります。
以下では、在宅避難と避難所生活それぞれの状況で具体的に役立つメンタルケアの方法を解説します。
どちらの場合も、「自分や家族の心を守る」 視点を持つことで、過酷な状況でも前向きに乗り越える力が湧いてきます。
在宅避難時のメンタルケア方法
自宅が無事であれば、避難所に行かず自宅で避難生活を送る「在宅避難」という選択肢があります。
自宅という慣れた環境で過ごせる利点がある一方、在宅避難者は行政や周囲から見えづらく、「孤立」しやすい面もあります。
そのため、在宅避難中は以下のポイントを意識しましょう。
- 基本ニーズを満たす:まずは飲料水・食料や電源などの生活インフラを確保し、困ったときに頼れる支援先を確認しておきます。自治体によっては在宅避難者向けに物資配布拠点を設ける場合もあるので、ラジオや行政発表で情報収集しましょう。安全な自宅であっても油断せず、非常用品や備蓄品で生活の安定を図ることが心の安心感につながります。特に夜はしっかり眠れるよう工夫しましょう。非常時は神経が高ぶって眠れない人も多いですが、アロマや普段使い慣れた寝具を活用する、明かりや音を遮断するなど環境を整え、少しでも身体を休めることが大切です。
- 正確な情報収集とデマ対策:在宅でいると、外の様子がわからず不安になりがちです。テレビやラジオ、自治体の防災無線などを通じて信頼できる情報を入手し、状況を把握しましょう。不確かな噂やSNSのデマ情報に振り回されないよう注意が必要です。企業防災の専門家も「真偽不明な情報が飛び交う中では、正確な情報提供が混乱や不安の軽減に重要」だと指摘しています。家族内でも情報を共有し、「いま自分たちが取るべき行動」が見えてくると心配が和らぎます。逆に常にニュースに張り付いて緊張するのも良くないため、一日に数回必要な時だけ情報チェックするなど情報との適度な距離感も心がけましょう。
- コミュニケーションで孤立を防ぐ:在宅避難者は周囲から見えにくいため、自ら積極的に声を上げることも大切です。近所に在宅避難者が他にいる場合は、お互い電話やSNSで安否確認をしたり困りごとを相談し合ったりすると安心できます。一人暮らしの場合も、行政の災害ダイヤルや支援団体の連絡先を控えておき、必要時には遠慮なく相談しましょう。被災者の心のケアでは「話を聴いてもらう」ことが非常に効果的であると専門家は強調しています。辛い気持ちや不安は誰かに話すだけでストレス緩和につながるので、家族や友人と連絡を取り合い、お互いに気持ちを打ち明ける時間を持ってください。もし周囲に話せる人がいなければ、公的な電話相談(厚生労働省や自治体が設置する 「心のケア相談」窓口 等)を利用する方法もあります。決して一人で抱え込まないようにしましょう。
- 普段の生活リズムを維持する:在宅避難では、避難所と違って自宅での日常を多少維持しやすい利点があります。可能な範囲で普段と同じ時間に起床・就寝し、食事や歯磨き、着替えなど日常のルーティンを守るように努めましょう。いつも通りの家事をしたり、室内でできる軽いストレッチや掃除をするのも気分転換になります。こうした日常的な行動は心に安定感をもたらし、先の見えない避難生活でも「自分でコントロールできることがある」という感覚が得られます。また、家族がいる場合は一緒に簡単な家事やゲームをする時間を作りましょう。特に子どもには「遊び」が何よりの日常です。安全が確保できる範囲で、おもちゃや代わりになる道具を用意して遊ばせたり、一緒に体を動かしたりして、子どもが少しでも普段通りに過ごせる工夫をしてください。
- 心のセルフケアを取り入れる:自宅でできるリラクゼーション法を試してみましょう。深呼吸や軽いストレッチ、ヨガ、好きな音楽を聴く、日記を書くなど、自分に合った方法でストレスを発散することが役立ちます。また、「今できていること」に目を向けて自分を褒める意識も大切です。不安な状況下ではできないことに目が行きがちですが、「今日は家族と笑顔で食事ができた」「必要な水を確保できた」など小さな達成を肯定的に捉えるよう意識してみましょう。そうした積み重ねがレジリエンス(心の回復力)を高めてくれます。
- 持病や心の不調への備え:家族に持病のある人や、平常時からメンタルヘルス上のケアが必要な人がいる場合は、在宅避難時に備えて事前に主治医や支援者と相談し、必要な薬を多めに備蓄しておくことが重要です。また、平時から服薬中の方は災害時にも飲み忘れないよう注意しましょう。精神疾患のある方の場合、環境の変化が大きなストレスになることがあります。お気に入りの毛布や音楽プレーヤーなど安心感を与える私物を非常袋に入れておき、在宅避難中もそれらを活用して心を落ち着けるようにします。行政や地域の福祉担当者による見守りが受けられるケースもありますので、障がい手帳や通院歴がある方は平時から自治体に情報を登録しておくと安心です。
以上のように、在宅避難では「自分たちで自分たちをケアする」要素が避難所より増えます。その分、事前の準備や心構えがものを言います。在宅でも決して独りぼっちではなく、地域や社会の支えにつながっていることを忘れずに、心の健康を守りましょう。
避難所生活でのメンタルケア方法
自宅が被害を受けたり安全が確保できない場合、多くの方は学校の体育館などに開設された避難所で生活することになります。避難所生活では大勢の被災者が一つ屋根の下に暮らすため、プライバシーの欠如や騒音、人間関係のストレスなど独特の精神的負荷がかかります。しかし同時に、周囲に人がいる安心感や支援物資を受け取りやすいといった利点もあります。このような避難所で心身の健康を保つポイントを見ていきましょう。
- ルールと役割分担で安心感を:避難所では、まず自治体職員や自主防災組織が定める生活ルールに従いましょう。配給の時間や物資の分配方法、寝床の配置、掃除当番など決まりごとがあることで、「お互い支え合って生活している」という安心感が生まれます。また余裕が出てきたら、自主的に避難所の運営を手伝ってみるのも良い方法です。物資配りや炊き出しの手伝い、掃除など自分にできる役割を担うと、「人の役に立てた」という充実感が得られ、受け身でいるよりも前向きな気持ちになれます。被災者自身が避難所運営に参加することは、居場所意識が高まりストレス軽減にもつながります。
- プライバシーと休息の工夫:大部屋で雑魚寝状態になりやすい避難所では、プライバシーの確保が大きな課題です。他人の目や物音が四六時中ある環境では、精神的にも落ち着きづらくなります。可能であれば支給されるパーテーション(間仕切り)やカーテンを活用し、自分と家族の生活空間に境界を作りましょう。段ボールや布で簡易的に仕切りを作ったり、アイマスクや耳栓を使って刺激を遮るのも有効です。行政も「避難所に落ち着けるスペースを設ける試み」を推奨しており、実際に体育館の一角に静かな休憩スペースを設けた事例もあります。少しでも一人になれる時間や場所を確保できれば、心を休めることができます。また、避難所では夜間照明が明るかったり物音がする場合もあるので、寝るときはアイマスクや耳栓、音楽プレイヤーなどを活用し、質の良い睡眠を取る工夫をしましょう。
- 情報共有とデマ対策:避難所では様々な噂や不確かな情報が飛び交いがちです。不安な心理状態では誤った情報に振り回されやすいので、公式発表や信頼できる情報源をみんなで確認し合うことが重要です。張り出される掲示板や定時のアナウンスには必ず目を通し、わからないことは遠慮なくスタッフに尋ねましょう。「○○が不足しているらしい」などといった未確認の話に過度に心配するより、必要なら自分で職員に確かめる姿勢が大切です。同じ避難所の人同士で情報を共有し、デマや誤解が広がらないよう協力することもストレスの軽減になります。正しい情報が共有されることで余計な不安や混乱を防げるので、結果的に皆の心にも余裕が生まれます。
- コミュニティの力を活用:避難所では「みんなで一緒に被災を乗り越えている」という連帯感が心の支えになります。できる範囲で周囲の人々とコミュニケーションを取り、お互い励まし合うようにしましょう。「ご飯食べられましたか?」など簡単な声掛けからで構いません。同じ境遇を分かち合える仲間がいると感じるだけで安心感が違います。特に高齢者や障がいのある方、妊産婦などは周囲の助けを求めづらいこともあるため、気にかけて声を掛けてみてください。その際、傾聴の姿勢を持つことが大切です。東京都のガイドラインでも「ストレス反応を軽減する最も良い方法は被災者の話に耳を傾けること」とされています。相手の話を途中で遮らずうなずきながら聞き、気持ちに共感を示すことで、語り手のストレスは驚くほど和らぎます。もし自分自身が不安で押しつぶされそうな時は、信頼できる誰かに話すか、避難所内に巡回している保健師や支援員に声を掛けて相談してみましょう。専門の「こころのケアチーム」や相談員が常駐・巡回している避難所もあります。遠慮せず、「話を聞いてもらう勇気」を持つことも大切なセルフケアです。
- 衛生と健康管理に気を配る:身体の不調は心にも影響します。避難所ではどうしても衛生環境が平時より悪くなりがちですから、意識して清潔を保つようにしましょう。可能なら毎日決まった時間に顔や身体を拭いたり、歯磨きを欠かさず行うことが大切です。着替えや洗濯が難しい場合でも、汗をかいたらタオルで拭く、手指の消毒をするなど工夫してください。特に感染症が広がると不安が増すため、マスクの着用や手洗いの励行で自分たちの避難所を清潔に保つことが心の安心にもつながります。また、避難所にボランティアの理容師・美容師が来てくれるケースもあります。髪を整えたりヒゲを剃ったりすると気分転換になりますので、そうしたサービスが提供された際は積極的に利用してみましょう。身だしなみを整えることは「日常」を取り戻す感覚を与えてくれ、自己肯定感アップにもつながります。
- トラブル対処と相談先:大勢が肩を寄せ合う避難所では、時に意見の衝突やトラブルも起こります。狭い空間でストレスを感じているので些細なことで怒りっぽくなる人もいますが、感情的な対立は避け、冷静に努めましょう。どうしても合わない人とは距離を取り、身近なスタッフにそっと相談してみるのも一つの方法です。また、避難所内でのDVやハラスメントなど 許されない行為 を目にしたら、決して一人で抱え込まず職員や警察に伝えてください。心のケアは何も我慢することではありません。安心・安全な生活環境を全員で作ることこそがメンタルケアの基本です。各都道府県には被災者向けの心の相談窓口が設置されており、電話相談や専門医の派遣などの支援も用意されています。必要であれば遠慮なくそうした 専門家の力 を借りましょう。たとえば厚生労働省はフリーダイヤルの「心の健康相談」電話を開設しており、平日の日中に無料で相談に応じています(※開設時間等は自治体発表をご確認ください)。心の不調も立派な「ケガ」と同じです。身体の怪我と同様、早めの手当てが大事だということを覚えておいてください。
家族・子どもの心のケアポイント
特に家庭でお子さんを抱えている場合、子どもの心のケアにも目を向けましょう。子どもは大人以上に状況が理解できず、不安や恐怖を感じています。しかし表現が未熟なため、一見普通に遊んでいても深く傷ついている可能性があります。「一番身近なおとな」である親や保護者だからこそできるケアがあります。日本ユニセフ協会は災害時の子どもの心のケアのポイントとして次の4つを挙げています。
- 「安心感」を与えること – 子どもに寄り添い、「もう大丈夫だよ」「ここは安全だよ」と繰り返し伝えてください。スキンシップを増やし、できるだけ一緒に過ごす時間を持ちましょう。子どもの不安な気持ちを笑ったり否定したりせず、優しく耳を傾けることが大切です。質問には分かる範囲で正直に答え、「どんなことがあっても守るよ」と伝えることで子どもは安心します。
- 「日常」を取り戻すことを助ける – 可能な範囲で普段の生活リズム(食事・就寝・遊びの時間など)を維持しましょう。避難生活でも子どもが安心して遊べるスペースや時間を作るよう工夫してください。お気に入りのおもちゃやぬいぐるみがあれば傍に置かせてあげましょう。普段からの習慣を続けることが、子どもの心に安定感をもたらします。
- 被災地の映像を繰り返し見せない – 大人がテレビで災害のニュース映像を見ていると、子どももそれを目にして強いショックを受ける場合があります。凄惨な映像は子どもの心に深い傷を残しかねません。可能な限り子どもの目に触れないよう配慮しましょう。同じ話題を大人が繰り返し話すだけでも子どもは敏感に感じ取りますので、子どもの前では必要以上に被災状況を話題にしすぎないことも大切です。
- 子どもの持つ回復力を信じて見守る – 子どもには本来、困難から立ち直る力が備わっています。大人が手をかけすぎて心配しすぎると、子どもは自分が「大変なことになっているんだ」と逆に不安を募らせることもあります。表面上は普通に遊んでいても、心の中ではストレスと闘っているかもしれません。しかし子どもは遊びや時間の経過とともに少しずつ心の傷を癒す力があります。大人は必要な安心を与えたら、あとは子どもの自己回復力を信じて温かく見守ることも大事です。「きっとこの子は大丈夫」と信じる姿勢が、子どもの心の安定につながります。
加えて、子どもは周囲の大人の様子に非常に影響を受けます。親が不安そうにしていたり悲嘆に暮れていると、子どもも敏感に感じ取って怯えてしまいます。もちろん無理に明るく振る舞う必要はありませんが、おとな自身がまず心のケアをすることが、結果的に子どもを守ることにつながります。適度に気持ちを発散し、周りの助けも借りながら、親御さん自身も心の健康に留意してください。「お母さん(お父さん)が笑顔でいる」ことが、子どもにとって何よりの安心材料になるのです。
平常時からできる心の備え
「心のケア」は何も災害が起きてから始めるものではありません。平常時からメンタル面の備えをしておくことで、いざという時の心の強さが格段に違ってきます。以下に、今から取り組める心の備えのポイントをまとめます。
- 家族で話し合っておく: 普段から家族や身近な人と「災害時に不安になったらどうするか」を話し合っておきましょう。お互いの連絡方法や集合場所を決めておくだけでも心配が減ります。また、「避難所ではプライバシーが無いかもしれないけど皆で助け合おう」「困ったときは遠慮せず助けを求めよう」など心の協力体制についても共有しておくと安心です。特に小さなお子さんには、「怖い時はぎゅっと抱きしめるからね」「○○ちゃんを守るよ」と日頃から伝えて信頼感を築いておきます。そうした事前の声掛けがあると、実際の災害時に子どもは「親が守ってくれる」と信じやすく、心理的な安定に繋がります。
- 非常用持ち出し袋に「心のケア用品」を: 非常袋や備蓄品を準備する際、心を落ち着かせるグッズも入れておきましょう。例えば家族の写真、お子さんの好きな絵本・おもちゃ、普段飲んでいるお茶のティーバッグ、アロマオイル、小型の音楽プレイヤーやイヤホンなどです。避難生活ではちょっとした癒しアイテムが心の支えになります。また、普段かかっている精神科や心療内科があれば診察券やお薬手帳のコピーも入れておくと、避難先で薬の処方を受けやすくなります。お気に入りの毛布や枕カバーなど「安眠グッズ」もあると安心です。非常袋にこうした心の非常食を忍ばせておけば、避難生活の質が少し向上し、メンタルヘルスにも効果を発揮します。
- ストレス対処法を身につけておく: 日頃から自分なりのリラクゼーション法をいくつか練習しておきましょう。深呼吸法、瞑想、軽い体操、ツボ押し、音楽鑑賞、ポジティブな言葉の唱和(日々「大丈夫」と唱える等)など、災害時にも実践できそうな方法がおすすめです。平時に習慣化しておくことで非常時にも活用しやすくなります。例えば、「4秒吸って7秒吐く」呼吸法を普段から就寝前に行っていれば、緊張状態でも思い出して実践でき、心拍数を落ち着かせるのに役立つでしょう。また、手軽にできるセルフマッサージ(こめかみや肩をほぐす等)も身につけておくと、避難所で緊張が高まったとき自分でケアできます。これらのスキルは家族みんなで覚えておくと、互いに教え合ったり一緒にやったりすることで一層効果的です。
- 地域の防災訓練や講習に参加する: 地域で行われる防災訓練や講演会に積極的に参加してみましょう。ただ避難経路を確認するだけでなく、心理的な備えについて学べる機会も増えています。災害後の心のケアをテーマにしたセミナーや、自治体主催のメンタルヘルス講習などがあれば家族やご近所と参加してみてください。専門家から直接アドバイスを聞くことで、「もし自分が被災したら…」と具体的に想像する訓練にもなります。また、顔見知りを地域で増やしておくこと自体が非常時の安心感につながります。災害時、人とのつながりが心の復興を早めることは東日本大震災など数多くの経験から明らかです。平常時から地域コミュニティに参加し、防災ネットワークを築いておくことは最高のメンタルケア策の一つと言えるでしょう。
まとめ:心の備えも防災の一部
災害は突然にやってきますが、心の準備ができている人は逆境に強くなれます。今回紹介した在宅避難・避難所でのメンタルケア方法や事前の心構えは、いざという時にきっとあなたとご家族の助けになるはずです。専門家の言葉を借りれば、「生活の再建支援がこころのケアの基盤になる」と言われています。すなわち、心のケアとは特別なことではなく、安全な暮らしを取り戻し、支え合うことそのものなのです。災害時にはまず自分自身を責めず、湧き上がる感情を受け入れてください。涙が出る時は無理にこらえず泣いて構いません。怒りや悲しみも自然な反応です。ただし、それらを信頼できる誰かに話すことを忘れないでください。話す相手がいなければ、各種相談窓口や支援団体があります。一人で抱え込まなければ、人の心は折れにくいものです。
一般家庭の主婦の方であれば、家族を支える立場ゆえに自分の不安を後回しにしがちかもしれません。しかしまずはあなた自身の心を満たし、元気でいることが、結果的に家族全員の心の支えとなります。この記事を参考に、「これは役に立ちそうだ」と思うメンタルケアの方法があればぜひ今日からご家庭で話し合ったり準備してみてください。「心の備え」も立派な防災です。物の備えと同じように心の備えにも目を向け、来たるべき災害に負けない強さを養いましょう。きっと「備えておいてよかった」と思える日が来るはずです。そして何より、大切な家族と自分自身の笑顔を守るために、今できる一歩を踏み出してみてください。あなたのその一歩が、非常時にかけがえのない心の支えとなるでしょう。心の防災準備を万全にして、いざというときも「きっと大丈夫」と乗り越えていきましょう。
お問い合わせ

